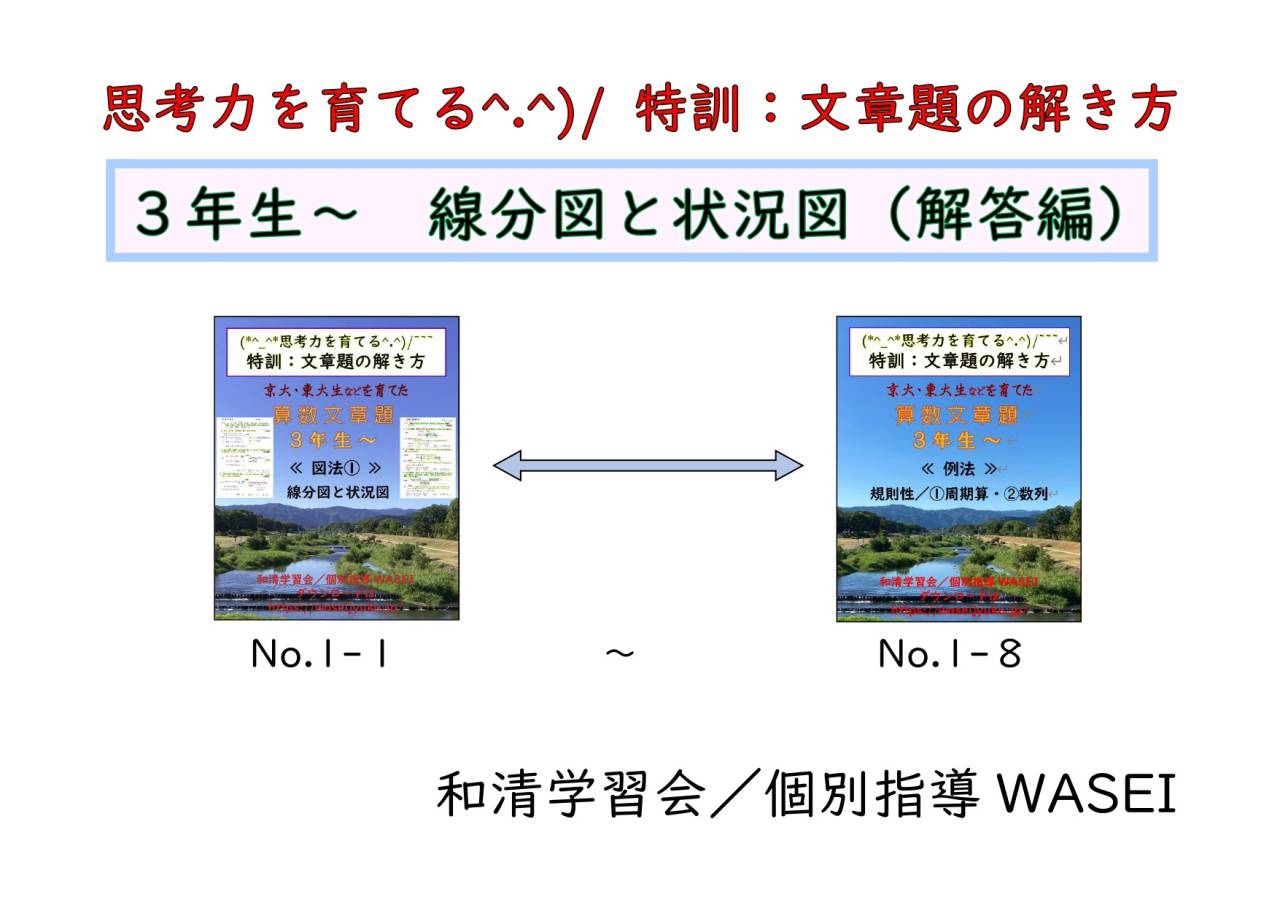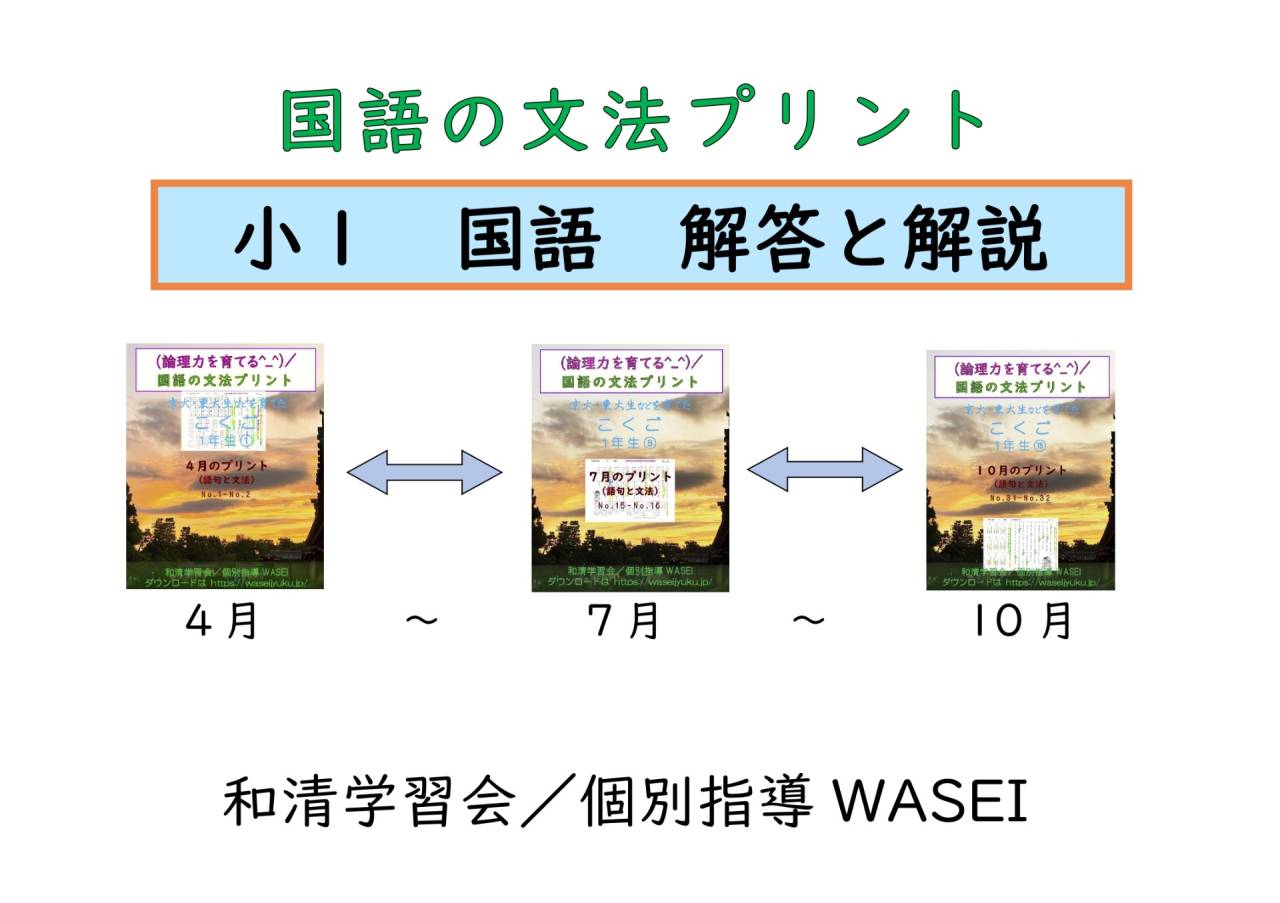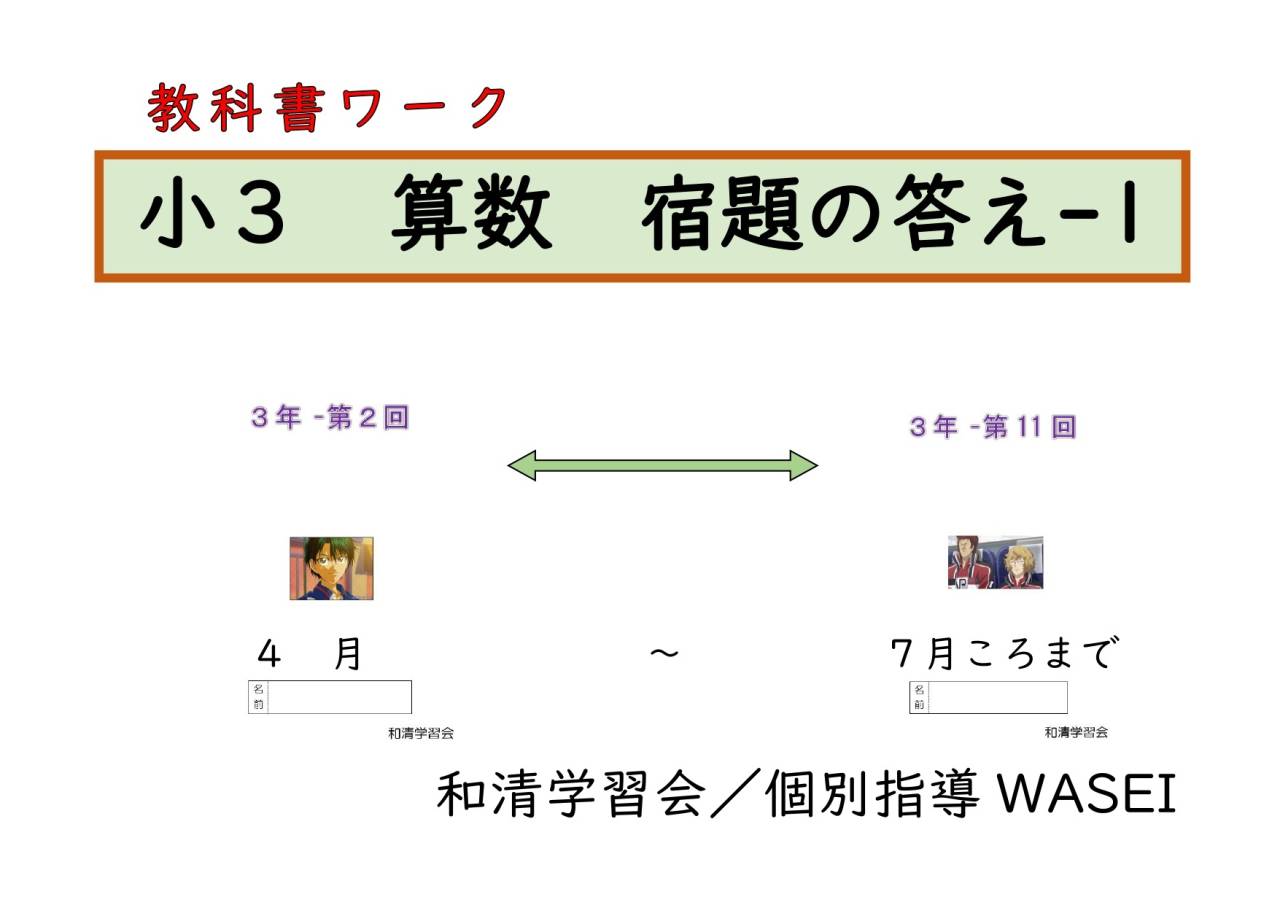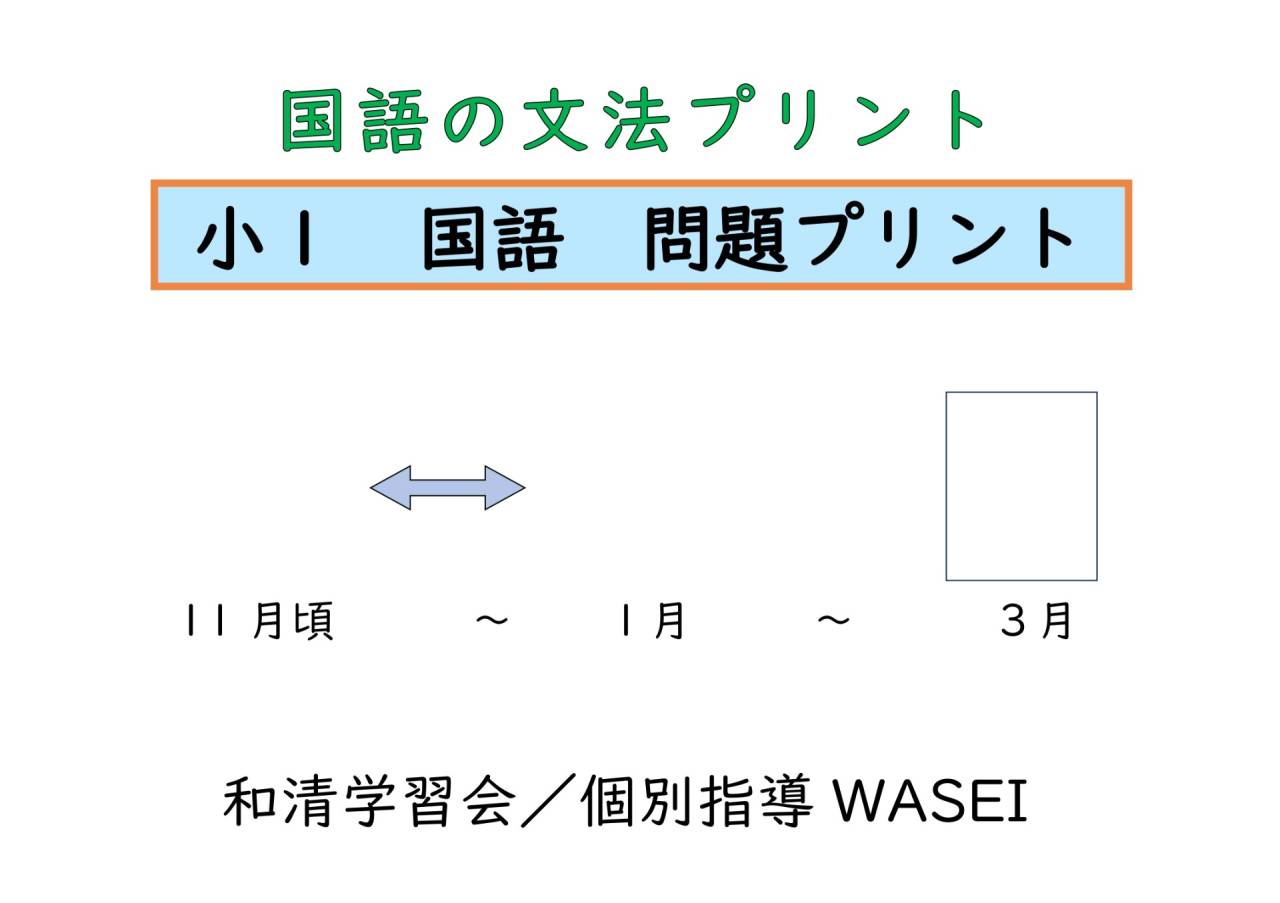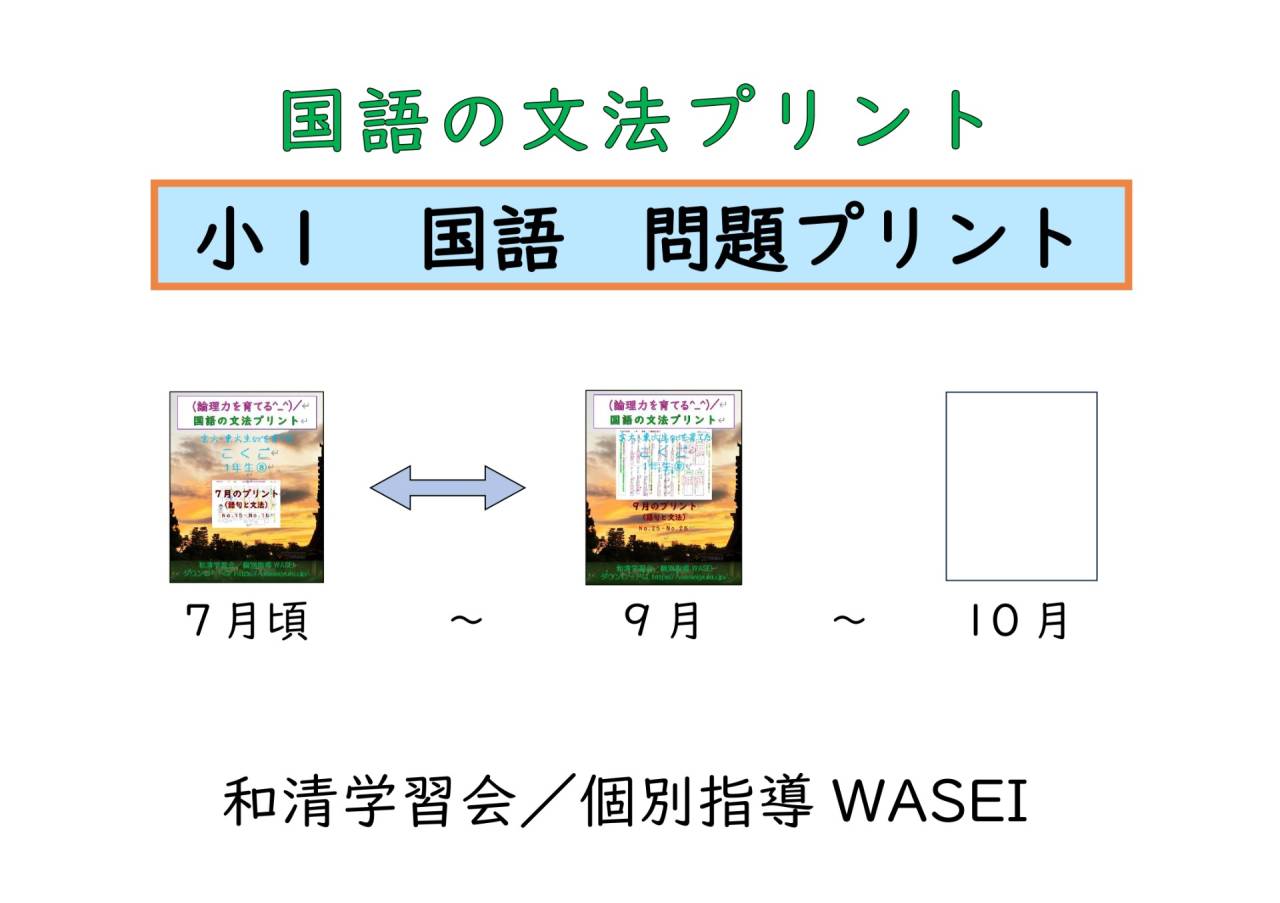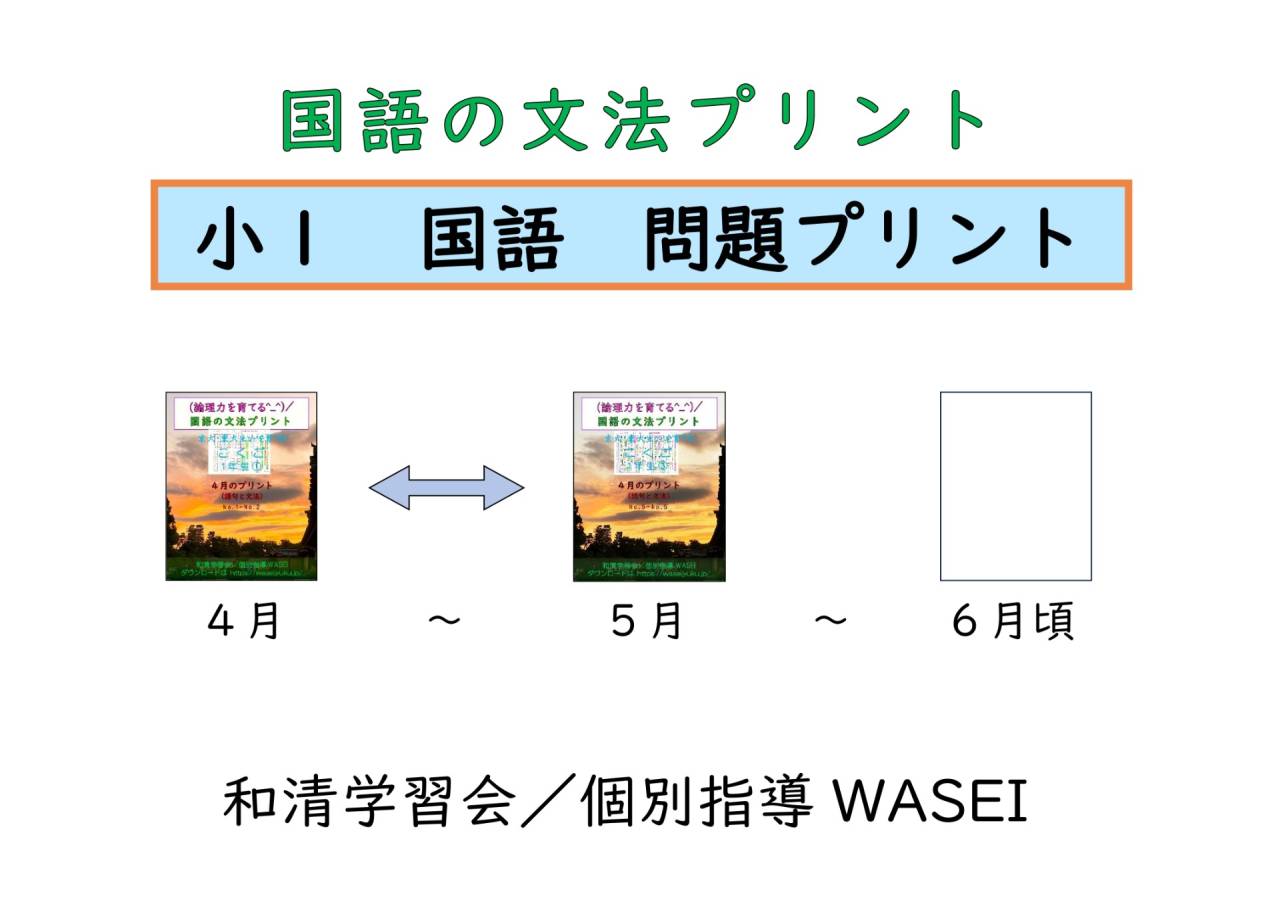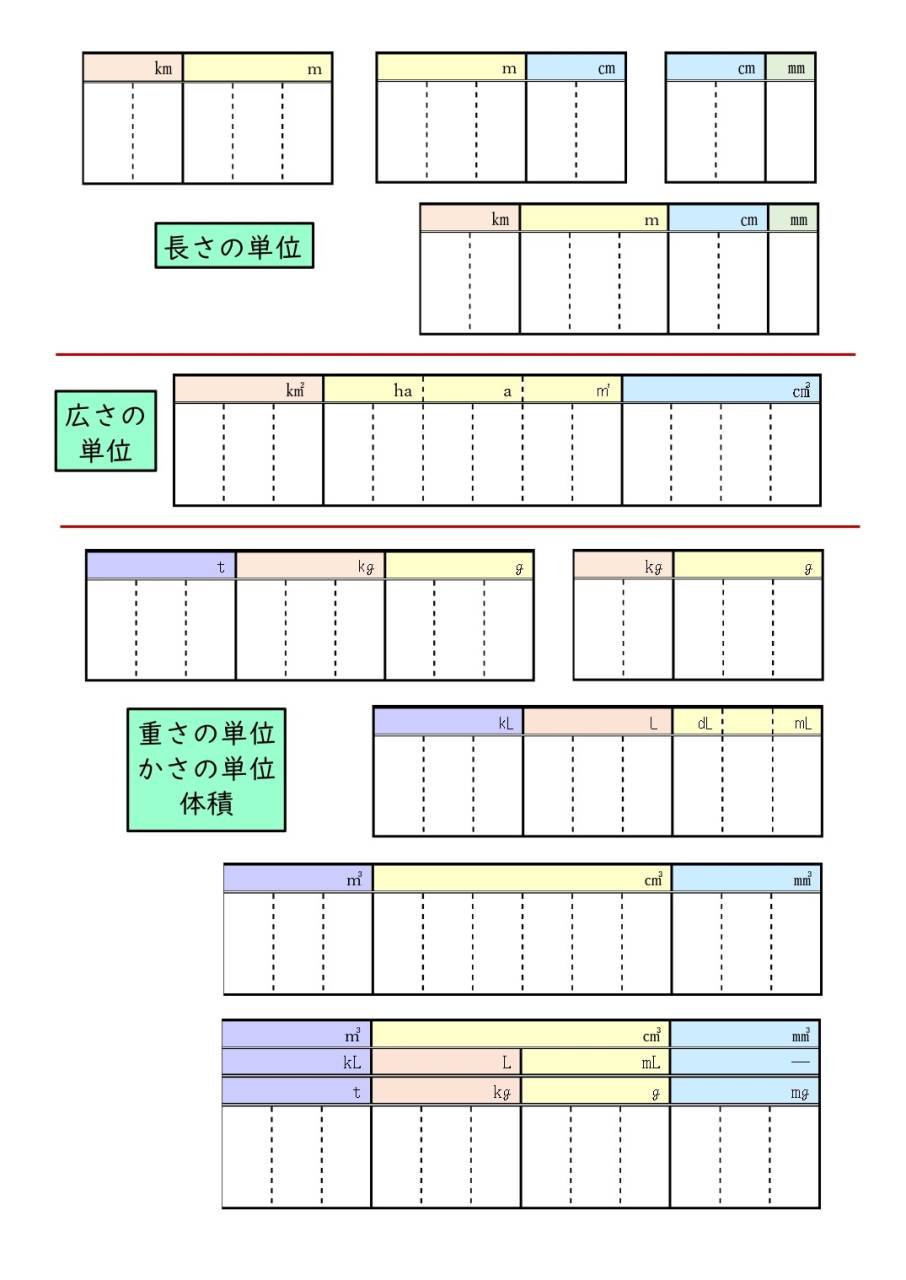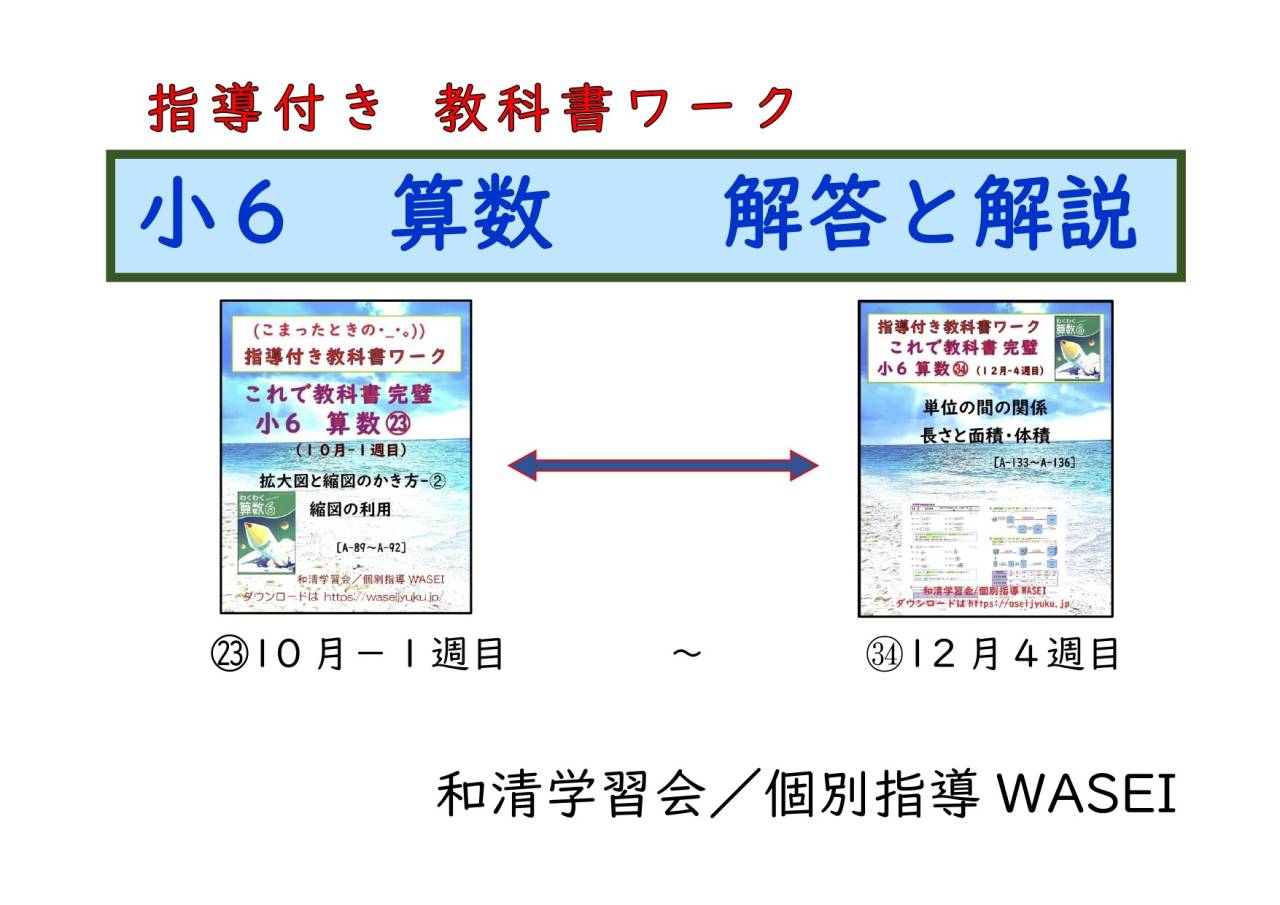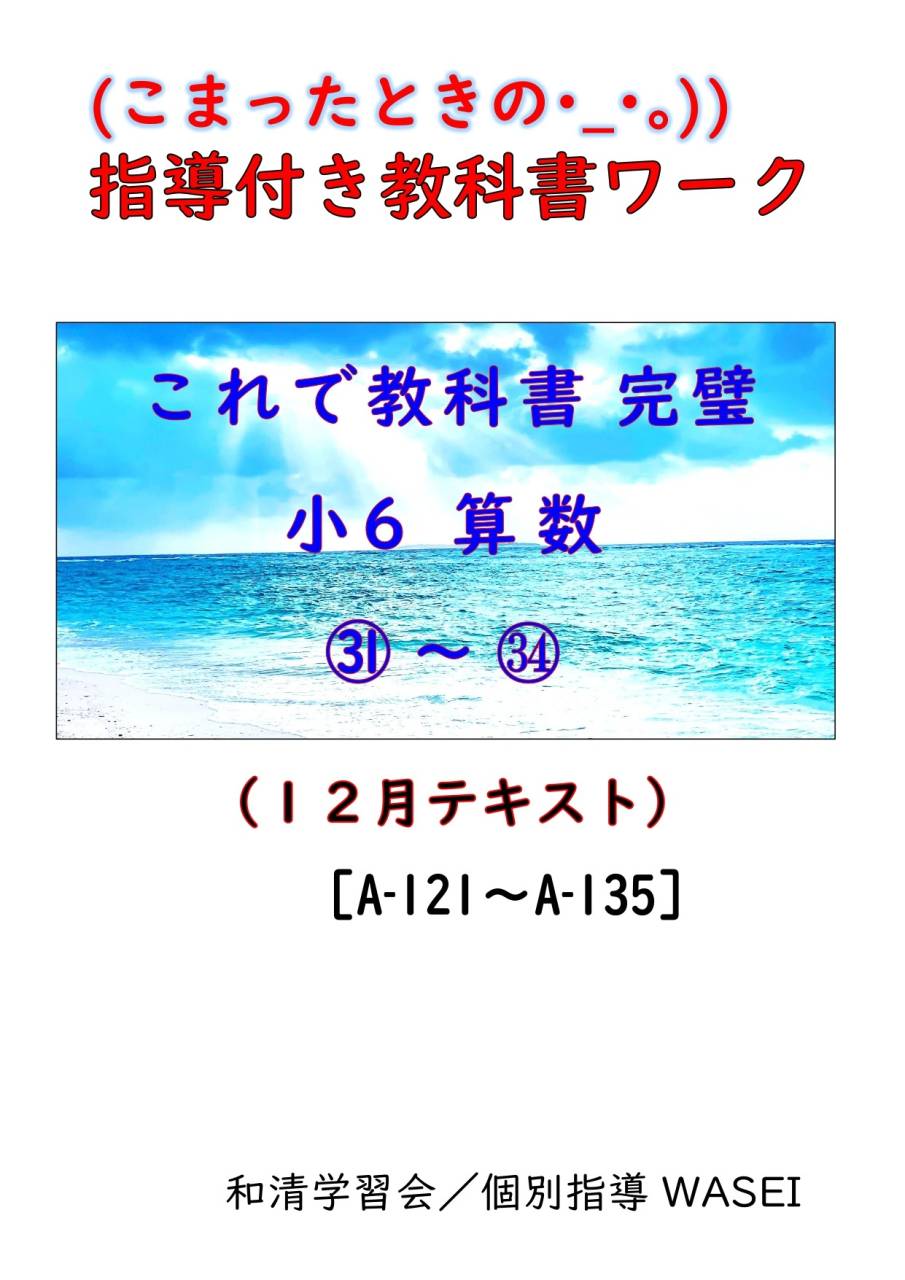予習・復習・テスト対策にぴったりな無料プリントを公開
GALLERY
テスト対策や予習、日々の復習などに役立つ無料プリントを掲載しています。練習問題を繰り返し解くことで、目標達成がグッと近くなります。ご自宅でも効率的に勉強を進められますので、ぜひ積極的にご活用ください。生徒様が安心して学べる環境づくりに力を入れており、温かみのある雰囲気を演出するだけではなく、ご自宅でも授業を受けられるオンライン指導にも柔軟に対応中です。
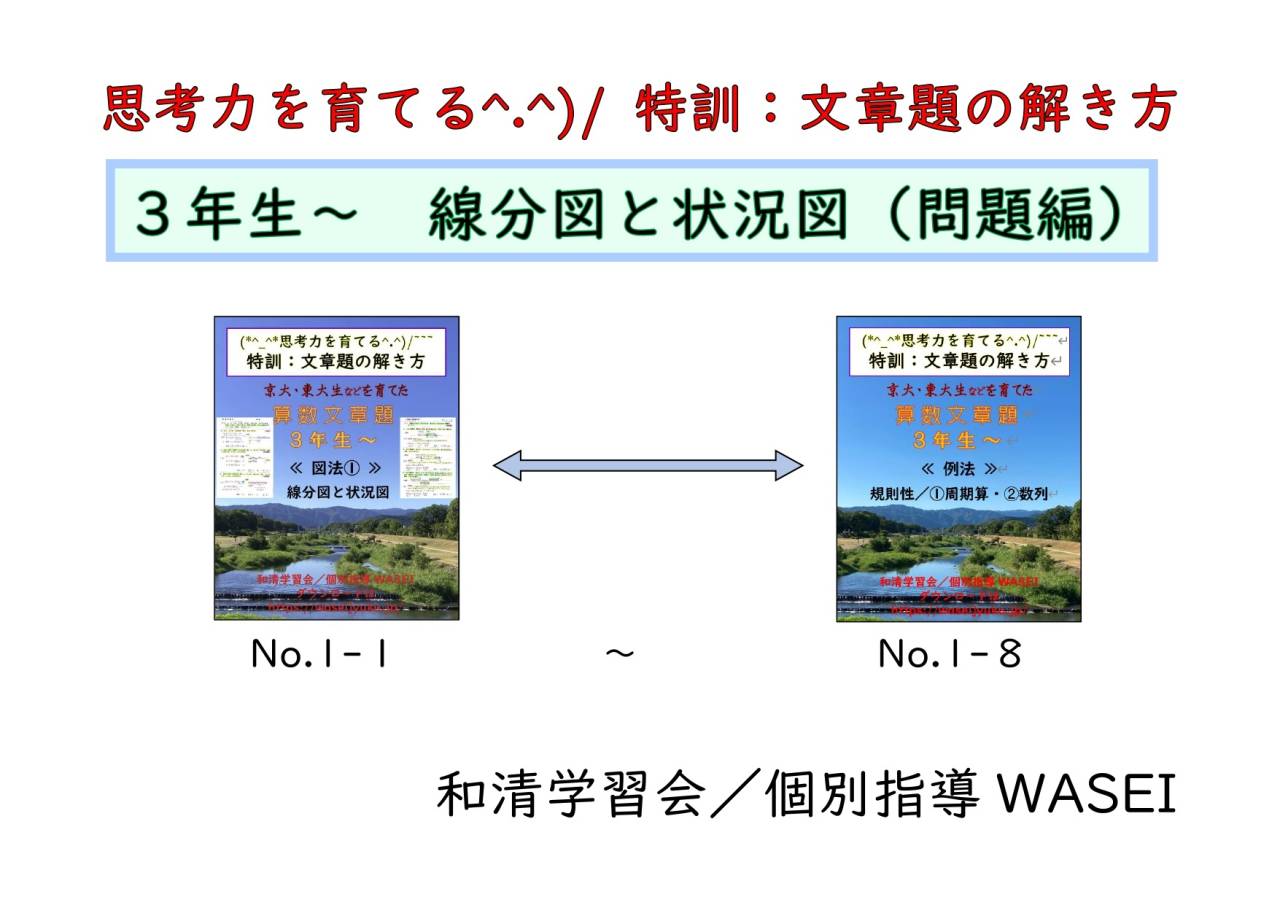
小3からの文章題特訓・図法と例法
このシリーズは、受験で必要な算数の特殊算を受験レベルまで引き上げるプリントです。小学3年生の計算が出来れば解けるように作ってあります。
1、受験算数の基礎を早い学年から身につけ、中学入試を有利に進めたい方。
2、現在学習している算数ではものたりないので、もっと難しい文章題にチャレンジしたい方。
3、中学入試対策の学習塾で、算数の文章題が分からなくなってしまっている5・6年生。
などが、いらっしゃいましたら、是非使ってほしい教材です。
問題を作成したのは、かなり昔ですが、このシリーズの学習をした生徒の多くが有名中学から有名大学に進んでいます。そして、現在はお医者さんや学校の先生、公務員などの職に就き活躍しておられます。
今回、約30年ぶりに詳しい解答・解説と指導法を付け足してインスタに投稿していきます。1冊が完成すればホームページから無料ダウンロードできるようにする予定です。
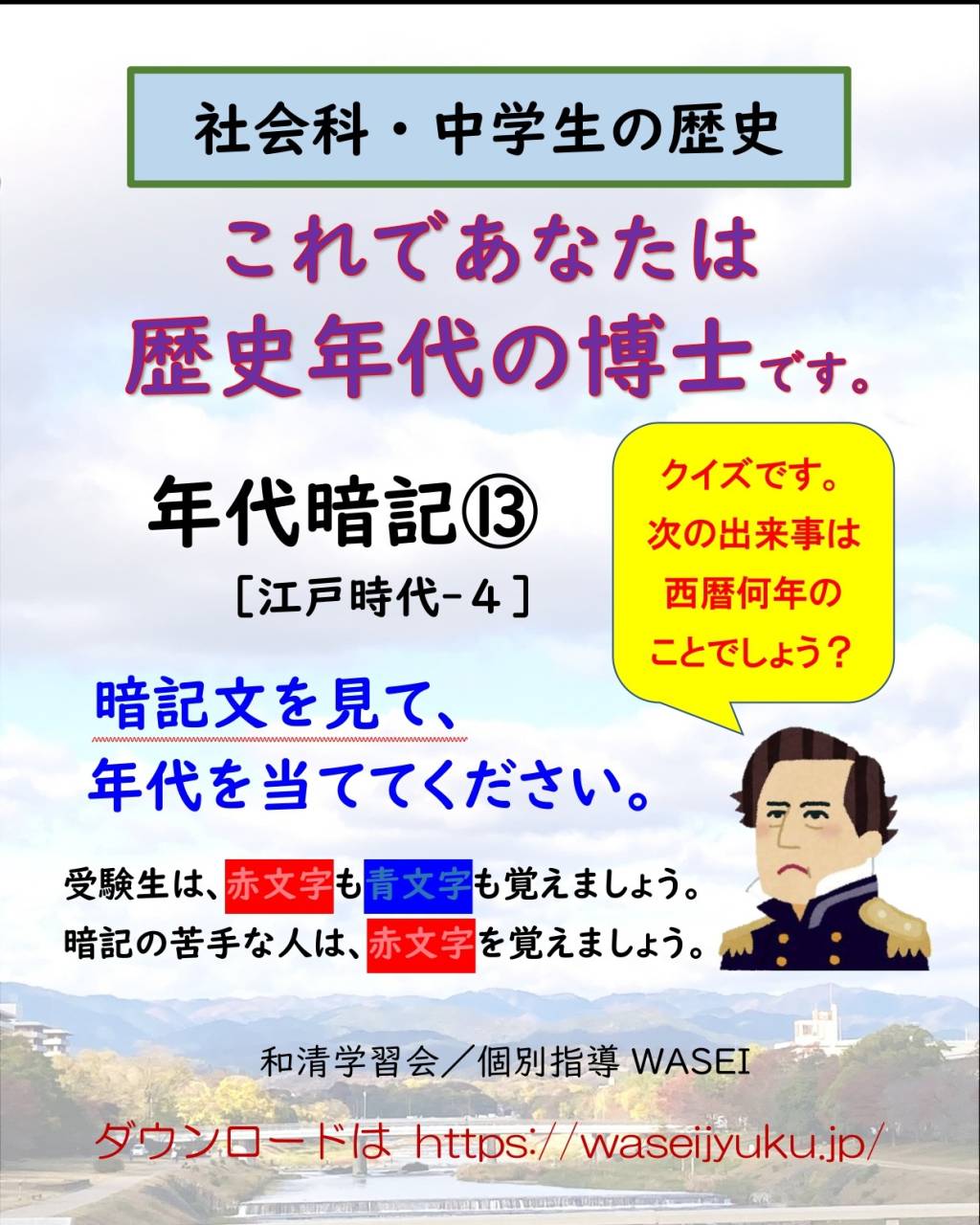
中学歴史・年代暗記⑬
中学生:社会 歴史の年代暗記⑬ 江戸の政治改革(後編)
1772年…田沼意次が老中になる・「意次は 非難何も 気にしない」
1782年…天明の大飢饉が起こる・「天明に 非難や不満の 大飢饉」
1787年…松平定信が老中になり、寛政の改革を始める・「定信の 非難の話 しちゃいかん」
1833年…天保の大飢饉が起こる・「天保の 人は散々 大飢饉」
1841年…水野忠邦が老中になり、天保の改革を始める・「忠邦の 改革初めは 良いテンポ」
【田沼意次】(前回の続き) 田沼は、年貢だけに頼る従来の政策を転換し、商品の流通や生産から得る利益によって財政の立て直しを図る。しかし、幕府中心の経済政策や賄賂の横行への批判が高まり、さらに東北地方の冷害や浅間山の噴火などによる天明の飢饉で、百姓一揆や打ちこわしが数多く起こるようになり、その責任を取り老中を退く。
【松平定信】徳川吉宗の孫。白川藩での実績から、老中となり「寛政の改革」を行う。
吉宗の政治を理想として、質素・倹約を掲げた。まず、都市に出稼ぎに来ていた者を村に返し穀物の栽培を奨励し、飢饉に備えて米を蓄えさせた。そして、借金に苦しんでいた旗本や御家人の生活難を救うため、町人からの借金を帳消しにさせ、そのかわり武士には倹約を徹底させ、学問・教養・武術を奨励した。また、幕府の権威を高めるため、庶民が読む出版物の内容を取り締まり、幕府の学校での朱子学以外の儒学を禁止したりした。
しかし、さかんに文武を奨励する定信に嫌気がさしたか、『世の中にか(蚊)ほどうるさきものはなし文武文武(文武文武)と夜も眠れず』や『白河の清きに魚の住みかねてもとの濁りの田沼恋ひしき』という狂歌を詠まれたりしている。
【天保年間】19世紀の前半は、しばしば凶作に見舞われた。1833年には天保の大飢饉が起こり、各地で一揆や打ちこわしが続発した。1837年、人々の苦しむ姿を見かねた大阪町奉行所の元役人であった大塩平八郎が乱を起こし幕府に強い衝撃を与えた。
【水野忠邦】社会の動揺と外国船の来航に対抗するため、享保・寛政の改革を参考に、社会の安定化と幕府の強化を目指して改革を始めた。「天保(てんぽう)の改革」
都市の農民を農村に返し、農民が商業に手を出すことを禁じた。物価を下げるため株仲間を解散させ、風紀をただすために出版を統制し、贅沢を禁じた。さらに、江戸や大阪周辺の大名領などを幕領にしようとしたりしたが、強引すぎるやり方は反発を買い、かえって幕府の権威は傾いた。忠邦の政策は2年余りしか続かなかった。